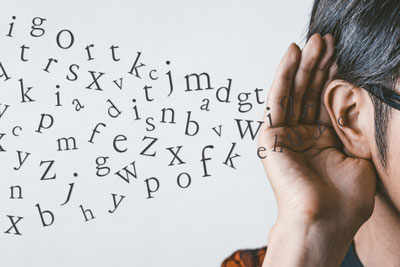
英語でコミュニケーションを取れる人が周りに何人かいるのですが、私自身は全然なのでいつも感心しています。そういえば、音楽を学ぶ過程は言葉を学ぶ過程に良く例えられますね。今回は、英語を話せるようになった人の向学心から、音楽への接し方のヒントを探ってみたいと思います。
英語を話せるようになった人(以降"できる人"と呼びます)を見ていて、まず思い当たるのが、普段から英語と接するように心掛けていることです。
例えば、英語のメールや英語の説明書の内容を理解する必要がある時、できる人は自分の力で読解しようと努めます。
私のように、翻訳サイトにコピペして手っ取り早く要点だけ拝借するようなことはやりません・・。
時間がないときはこの限りではないかもしれませんが、自分から英語の海に飛び込んで行くことで、少しずつ鍛えられるんだと思います。
できる人は他にも、洋画を見る時に吹き替えでなく字幕を選んだりしますね。
さらに日本語字幕ではなく英語字幕にしたり、さらに字幕自体なしで見る上級者も存在します!
趣味の分野でも英語への学習意欲を忘れず、レベルアップを図ろうとするなんて、頭が下がります・・。
これらを音楽に置き換えるとどうなるでしょうか。
- 曲のコード進行を知りたい時、すぐにネットで検索したり楽譜を探すのではなく、自分の分かる範囲で耳コピしてみる。
- タブ譜ではなく五線譜を読んで弾いてみる。
- そもそもタブ譜の付いていない五線譜だけの譜面を読んでみる。
他にも色々と考えられそうですね。
苦手だからといって敬遠していたら、いつまで経っても上達しないという点が英語と共通しています(うっ、頭が痛い・・)。
できる人はさらに、英語を使う場所に積極的に足を運んでいます。
留学したり英会話教室に通ったり、英語を使うコミュニティに参加したりといった具合です。
実際に英語を聞いたり話したりすることで、体に染み込ませるような感じでしょうか・・。
これは音楽だと
- 音大に行く
- ギター教室に通う
- ライブに行く
- オープンマイクで演奏する
- バンドを組んで練習する
といったことに置き換えられそうです。
人によってできる範囲が違うのでどれが良いかは決められませんが、とにかく外に出て外部からの刺激を受けることが大事だと言えそうです。
あと1つ、できる人が実践しているのが、自分の言葉で話すことではないでしょうか。
言葉はコミュニケーションの道具なので、そんなことは当たり前と言われるかもしれません。
しかし、知っている単語や表現を組み合わせて自分の気持ちを伝えるのは、かなり高度な技術が必要だと思います。
用意しておいた原稿を読むだけでは、中々その技術は身に付きません。
最近、「言語の本質(今井むつみ・秋田喜美 著、中公新書)」という本を読みました。
その中で言語の特徴がいくつか語られているのですが、最も印象深かったのが、言語は自分で学習のサイクルを回していけるという点です。
例えば、既存の言葉を組み合わせて自分なりに表現したり、語尾の変化の法則性を汲み取ってまったく別の言葉に応用してみたり、2つの単語をくっつけて新しい言葉を作ったり・・といった感じです。
もちろん伝わらなかったり、その言語の歴史的に間違った表現になっていたりすることもあります(例えば"an egg"ではなく"a egg"としてしまうなど)。
しかし、他の話者の言葉を聞いたり指摘を受けて修正したりを繰り返していくと、多くを教わらなくても自在に言語が扱えるようになってくる、とのことです。
自分の言葉で話す、そして学習のサイクルを回す・・。
何か音楽を演奏する際の重要なヒントが隠されてそう気がしないでしょうか?
あえてと言うか、はっきりとした答えも出せませんし、ここは無理に音楽と類推することはやめておこうかと思います。
しかし、言葉と音楽の類似性がまた少し感じられて、とても興味深いですね。



