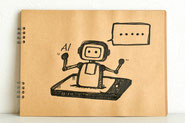みなさんは、ギターでコピーしたりアレンジしたりする曲を、どのように選んでいるでしょうか。好きな曲をやれば良いのでは?と思われるかもしれませんが、ギターをやればやるほど、選曲の幅は狭くなっていくようです・・。
ギターを始めた頃や、自分で少しギターパートをアレンジするようになった頃は、自分の好きな曲に取り組むことが多いと思います。
その曲があまり有名ではないアーティストの曲でも、ヒットシングルの影に隠れたアルバム曲でも関係ありません。
とにかく自分がやりたいからやる!
難易度が高いからとか、譜面がないからとかの理由で諦めることはあるかもしれませんが、基本的には世に存在する数多の曲の中から好きに選びます。
これは、テクニックが発展途上で思ったように弾けず、下がり気味になるモチベーションを、曲に対する情熱で補完する意味合いもあるかもしれません。
次に、もう少しギターに深入りして、人前で演奏するようになったらどうでしょうか。
自分が弾きたいかだけではなく、聴く人に楽しんでもらえるような選曲をする必要がでてきます。
自然とスタンダード曲やヒット曲を選ぶことが増えますし、例えマイナーな曲であっても、演奏する場所や季節、聴いてくれる人などにゆかりがある曲を選ぶようになります。
もしかしたら事前に曲を指定されたり、リクエストされることもあるかもしれません。
なんにせよ、選曲の幅は少し狭くなっていると言えそうです。
さらに深入りして、ギターが収入の柱となってくるとどうでしょうか。
ライブをするにしても、CDを作って販売するにしても、動画を配信するにしても、できる限り多くの人に聴いてもらわないといけません。
単に有名な曲というだけではなく、時代の流れに乗っていることも重要になってきます。
さらに、著作権など権利面の配慮も必要になります。
例えばYouTubeに演奏動画をアップする時、著作権で保護されたコンテンツが含まれていないかがAIによってチェックされます。
保護されたコンテンツだとみなされると、その動画の広告収入が著作者に入る場合もありますし、下手すればアップロード自体ができない場合もあります。
そういったことを考慮しながらとなると、選曲の幅はかなり狭くなっていると言えそうです。
自分の好みだけで選曲ができなくなる様子は、何となく勉強と仕事に通ずる部分があります。
学生時代は、自分が興味のある分野について、より深く勉強できるように選択することができました。
高校ではいわゆる文系・理系の他に、農業系や工業系、スポーツ系などが選択肢として存在します。
さらに大学や専門学校では、理系の中でも工学系の情報科学・・のようにさらに専門性の高い分野に踏み込んで行くことができます。
入学の難易度や学費の問題もありますが、自分の好きなことができるようになっていますね。
しかし、卒業論文を書く辺りから少しずつ制約が出てくるようになります。
すべての卒業論文に該当するかは分かりませんが、私の時は論文に"新規性"を強く求められました。
既存の研究にない新しさがあるかということですが、これが中々大変です。
そもそも、既存の研究にどのようなものがあるかを知らないと、自分のやっていることに新規性があるかどうかすら分かりません。
良いアイデアだと思って持って行っても、「そんなもん昔からあるよ」と研究室の先生に一蹴されることもしばしばでした。
要は、好きなことをやるだけでは成り立たたない状況ということですね・・。
さらにいざ就職して働くとなると、その企業(自治体かもしれませんが)の部署に特化した仕事をしなければなりません。
学生時代にやっていたことが少しは考慮されて配属されると思いますが、そのまま活かせることは少ないように思います。
仕事になるようなことは、外の人から見るとマニアックに見えることがほとんどなので・・。
例えば自動車のシートを製造している会社の開発部署にいたら、シートの安全性や座り心地や製造性などを、四六時中考えることになると思います。
モノを設計するのがなにより好き!という人はいるかもしれませんが、自動車のシートがなにより好き!って人はほとんどいないのではないでしょうか(想像ですが・・)。
そんな中で生き生きと働いている人は、あまり自由度がない仕事の中にも、何か面白さや工夫の余地を見出したりしているんだと思います。
以上、別に何か言いたかったことがあった訳ではないんですが、選曲に関してあれこれ考えていたことをまとめてみました。
何となく、自分のやりたいことをやるのが至高!のような風潮が世の中にある気がしますが、実際はやればやるほど選択の幅が狭くなっていくのではないかと思った次第です。
逆に考えると、その狭い幅の中でどれだけのパフォーマンスを発揮できるかが大事になってくるのかもしれませんね・・。