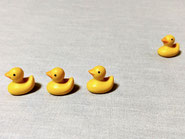昔はバンドメンバー全員が集まり、「せーの」で一発録りすることもあったようですが、現代ではクリックに基準にして、各パートを個別に録音するのが普通です。つまりクリックに合わせられないと話にならないということですね・・。今回はその下地となるメトロノームを使った練習について書いてみます。
先ほど録音する時に規則的なテンポで弾けることが重要だと書きましたが、録音以外の生演奏などでも状況は変わらないと思います。
と言うのも、今はクリックに合わせて作られた音楽を聴くことが多く、リスナーの耳がそれに慣れてきていると考えられるためです。
音楽をやっていないリスナーでも、わずかなリズムのズレを敏感に感じ取る傾向が強くなってきていると感じます。
特に、バンドのドラムのような基準がない、ソロギターや弾き語りなどの1人で演奏するスタイルは、注意が必要になりそうです。
そういったスタイルだと比較的自由にリズムを変更することができるので、例えばちょっとタメて弾くことも簡単にできますよね。
しかし、リスナー側にはそれがモタっているように聴こえている場合もあります・・。
あえてずらしているという風に聴かせないといけないため、基本的には正確なリズムを刻んでいることが必須になってきます。
私自身が最近同じような状態になってしまい、しばらくやっていなかったメトロノームを使った練習を再開することになりました。
演奏中はしっかりとリズムをコントロールできていると思っていたものの、いざ録音して聴いてみると、走っていたりモタっていたりしているように聴こえたんです・・。
特にスローテンポの曲でそれが顕著で、まだまだ練習が必要だと痛感しました。
という訳で、ここからはタイム感を改善すべく行ったメトロノームを使った練習の内容と、これまでギタリストの諸先輩から教わったメトロノームの有効な使い方をご紹介したいと思います。
使用するメトロノームは、昔ながらの振り子が左右に動く機械式でも、電池で動く電子式でも、スマホのアプリでも、DAWに付属のクリック機能でも、何でも構いません。
練習環境に応じたものを選んで頂ければと思います。
また、電子式やアプリのメトロノームは、拍子の設定が可能になっているかと思います。
例えば4/4に設定すると、ピッポッポッポッ、のように頭の拍だけ異なる音が出せます。
私は基本的にすべて同じ音色(設定だと1/1のようになる)にしていますが、これもお好みで選択頂ければと思います。
慣れない5拍子の曲をやる場合などは、頭の拍が分かった方がやりやすいかもしれません。
スローな曲の練習
まずは私が取り組んだ、スローな曲でのメトロノームを使った練習方法です。
録音によるチェックで大分リズムが改善されたことが確認できたので、一定の効果はあるはずです!
ソロギタースタイルの演奏曲に適用しましたが、弾き語りやアンサンブルの曲でも同じように参考にして頂けると思います。
テンポとしては、BPM=60くらいの曲を想定しています。
ちょうど、1秒で1拍となるテンポですね。
メトロノームを鳴らしたり時計の秒針で確認してもらうと分かりますが、かなりゆったりしたテンポに感じます。
最初からBPM=60のメトロノームに合わせて弾いても、中々クリック(メトロノームの音)と演奏が噛み合いません。
あまつさえ、メトロノームの方がずれているようにも感じてしまいます(そんな訳はありません・・)。
このままではまずいので、倍のBPM=120で鳴らすことにします。
これだとクリックが2倍になり、拍のウラでも鳴ってくれることになります。
あいまいになりがちな裏拍が示されることにより、演奏のどこがずれているのかが分かるようになりました。
特に録音して聴き返すと客観的に判断できるので、たまに録音してチェックしつつ、演奏にフィードバックします。
しばらくこのBPM=120で練習を続けます。
ここまででも、最初よりはかなりリズムが改善されているはずです。
しかし念のために、BPM=60に戻した状態でも練習しました。
と言うのも、演奏中に体で感じているテンポはBPM=60で、120ではちょっとせわしないためです。
BPM=120でしっかり練習したおかげで、BPM=60でも最初みたいにメトロノームがずれているように感じることはほとんどありません。
本来のゆったりしたビートを感じつつ、リズムの正確さだけでなく感情も込められるように練習を続けます。
もちろんここでも、録音のチェックと演奏へのフィードバックを繰り返します。
録音を聴き返して問題なさそうであれば、いよいよメトロノームを卒業・・といきたい所ですが、もうひと押ししました。
これまではっきりと聴こえていたメトロノームの音量を、下げての練習です。
ジャストのタイミングで演奏をすると、メトロノームが聴こえなくなるくらいの音量に設定して、追い込みをかけます。
これまで頼りにしていたメトロノームから、少しずつ独り立ちするような感じでしょうか・・。
そして最後はもちろん、メトロノームなしでの練習です。
ここでようやく、あえてリズムをずらすような演奏にも挑戦できるようになります。
録音とフィードバックを繰り返し、必要であればメトロノームを使った練習に戻ることも視野に入れつつ、仕上げを行います。
以上がスローな曲の練習手順になります。
メトロノームの基本的な機能を使うだけなので、メトロノームを使ったことがない方もだまされたと思ってトライしてみて下さい!
少し長くなってきたので、その他のメトロノームを使った練習アイデアは次のブログで【後編】としてまとめたいと思います。
メトロノームを傍に用意しつつ、ぜひご覧頂ければと思います。